
夏の風物詩である七夕祭り。
七夕の飾り付けは、豊かな意味や願いを込めたアイテムで、日本の伝統文化を彩ります。
ひし形つなぎ、紙衣、巾着、投網、吹き流し、折り鶴、スイカ、輪つなぎなど様々な種類の飾りが存在し、それぞれに独自の意味合いがあります。
また、短冊なども七夕の飾りとして欠かせません。
この記事では、特にひし形つなぎやスイカを飾るや意味や七夕飾りの意味や種類、短冊の書き方や短冊の簡単な作り方を紹介します。
一緒に七夕の風習や祭りの楽しみ方を探ってみましょう。
七夕飾りの名前と種類
七夕には、笹に飾る笹飾りや七夕飾りがあります。
七夕飾りは大きく7つの種類に分けられ、それぞれに名前と意味があります。以下にその種類と願いを紹介します。
1:紙衣(かみごろも)

紙衣は、棚機女(たなばたつめ)が織り、神に捧げる衣です。
七夕竹の一番上に吊るされることが多いです。身代わりとして病気や災害を除くといういわれがあり、昔は母親に教わり、布で縫われた紙衣でした。
現在では紙で作られますが紙衣は、裁縫や手芸の上達を願うものでした。
2:巾着(きんちゃく)

巾着は昔、腰から下げる財布のようなものでした。
商売繁盛や富貴、成功を願いながら、貯蓄の心を育て、無駄遣いを戒めます。
3:投網(とあみ)
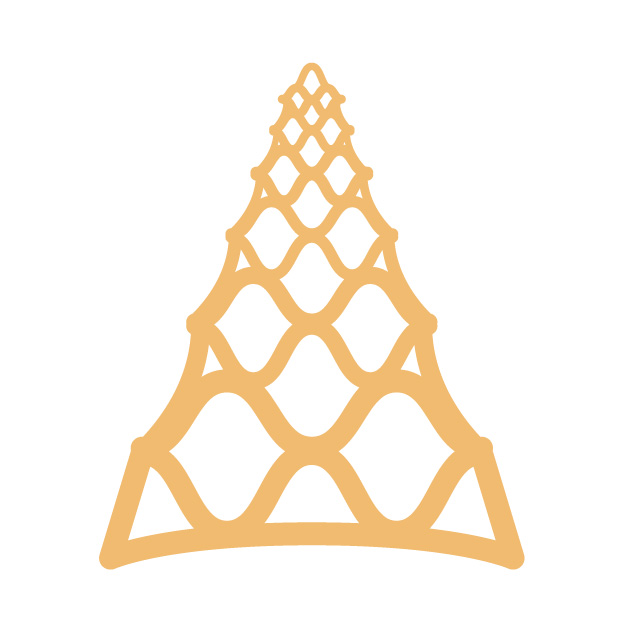
投網は、昔から魚介類の重要なタンパク源である豊漁を祈るために飾られます。
4:吹き流し

吹き流しは、錦糸をたらした形をしており、風に揺れる様子が美しい飾りです。吹き流しの特徴は、その糸が願いの糸とされていることです。
糸は、人々の願いや願望を象徴しています。吹き流しの糸は風になびき、願いを運んでくれると考えられています。
風に揺れる吹き流しの姿は、人々の心の中にある願いや希望を表現しているのです。
吹き流しには様々な色や模様が使われており、それぞれに意味が込められています。
たとえば、赤色は幸運や繁栄を象徴し、青色は健康や平和を表しています。
また、吹き流しの形状にも特徴があり、一つ一つのデザインには地域や伝統に関連した要素が含まれています。
5:折り鶴

折り鶴は、昔は家の長老の年の数だけ折られ、延命長寿を願うために飾られました。
折り鶴の折り方を通じて、教わる心や人に教える喜びを学ぶこともあります。
現代でも、家族の長寿と健康を祈って飾られます。
6:屑籠(くずかご)
屑籠には、7つの七夕飾りが作り終えた裁ちくずや紙くずが入れられ、清潔さと節約の精神を育て、物を粗末にしない心を育みます。
7:色紙短冊

色紙短冊は、昔は早朝にカラトリの葉っぱについた夜露で墨をすり、師に教わった文字や詩を書いて願い事をしました。
学問や書、手習いの上達を願います。
今では、率直に願い事を書き成就するよう願います。
といった基本の7つのかたちには、無病息災や、商売繁盛までさまざまな願いが込められています。
他にもひし飾りや輪つなぎ、笹飾りなどがあります。これらは天の川を象徴しています。笹には季節に合ったすいかやなすなども飾られます。これらは豊漁や豊穣を祈るためです。星は、みんなの願いが星に届くようにという願いが込められています。
また、織り姫と彦星を願って続く永遠の愛情を表す飾りもあります。
以上が古来の七夕飾りの意味と種類です。これらの意味を知ることで、七夕飾りを楽しむことができます。
七夕飾りのひし形つなぎやスイカの意味
ひし形つなぎの意味
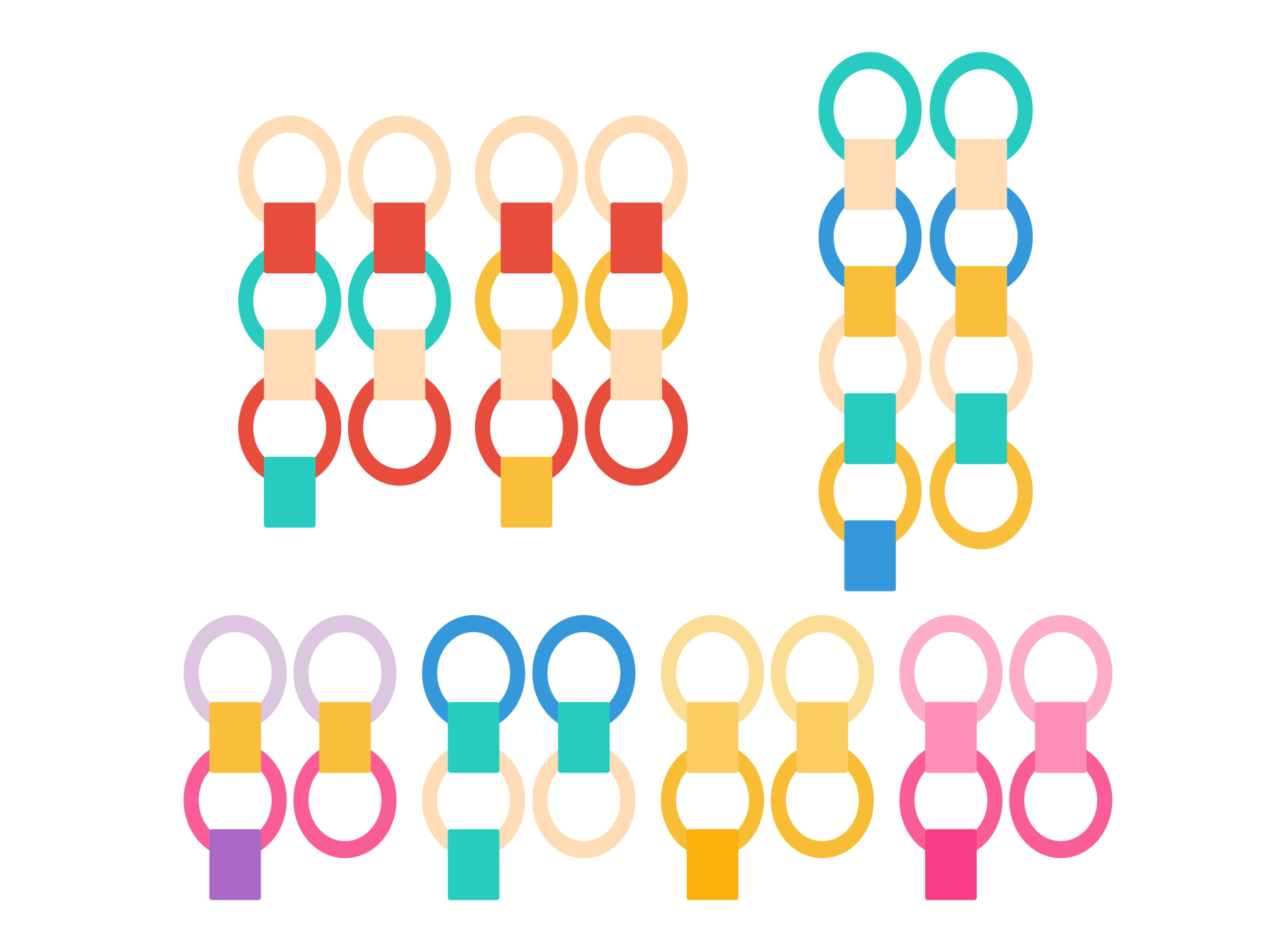
七夕飾りのひし形つなぎは、特定の意味を持つ飾りの一つです。
ひし形つなぎは、短冊などの紙をひし形の形に切り、連結させて作られる装飾です。
輪つなぎも同様の意味をなします。
このひし形つなぎや輪つなぎには、以下のような意味が込められています。
繋がりと結びつき
ひし形は連結されている形状をしており、個々のひし形が一つに繋がっていることを表現しています。
これは人々や家族、コミュニティの絆や結びつきを象徴しています。
願い事の連鎖
各ひし形には願い事や願望が書かれることがあります。
連結されたひし形つなぎは、それぞれの願いが連鎖していることを表しています。
一つの願いが他の願いに影響を与え、つながりながら願い事が実現することを願っています。
縁起の良さ
ひし形は、縁起が良いとされる形状の一つです。
そのため、七夕の飾りとしてひし形つなぎを用いることで、幸運や縁起の良い出来事を呼び込むことを願っています。
ひし形つなぎは、色とりどりの紙を使って楽しく飾り付けることができます。
また、子供たちにとっても簡単に作ることができるので、七夕の行事やイベントでよく見かける飾りの一つです。
七夕のひし形つなぎは、繋がりや結びつき、願い事の連鎖、そして縁起の良さを象徴しています。
これらの意味を持つひし形つなぎを飾ることで、人々の絆を感じながら願いを込めることができます。
七夕飾りでスイカを飾る意味
七夕飾りにスイカを飾る意味については、特定の伝統的な意味があるわけではありませんが、スイカは夏の象徴的なフルーツとして使用されることがあります。
そのため、七夕の季節にスイカを飾ることで、以下のような意味や願いを込めることができます。
夏の訪れと季節感
スイカは夏に収穫される代表的なフルーツです。七夕は夏の季節に行われるイベントであり、スイカの飾りは季節感を表現し、夏の訪れを感じさせます。
豊穣と豊かさ
スイカは大きくて豊かな実を持つ植物であり、豊穣や豊かさの象徴とされることがあります。
スイカを飾ることで、豊かな収穫や繁栄を願う意味を込めることができます。
涼しさと爽やかさ
夏は暑い季節ですが、スイカは水分を多く含んでいるため、涼しさや爽やかさを感じさせます。
スイカの飾りは、その涼しげなイメージを伝え、暑い夏を快適に過ごすことを願う意味を持つことがあります。
ただし、七夕の飾りにスイカを使うかどうかは、地域や個々の好みによって異なります。
伝統的な七夕の飾りではないかもしれませんが、スイカの飾りは楽しくカラフルな雰囲気を醸し出し、子供たちにも喜ばれることがあります。
七夕飾りにスイカを飾ることで、夏の季節感や豊かさ、涼しさを表現し、また個々の願いを込めることができます。
それぞれの家庭や地域の独自の風習やアレンジによって、スイカの飾り方や意味合いが異なるかもしれません。
七夕飾りをする意味
七夕の飾り付けには、中国から伝わった習慣が主になっています。
日本では、七夕の節句に飾る七夕飾りを、日本独自のスタイルに変えてきました。
実は、五節句と呼ばれる行事では、それぞれ特定の植物が関連しています。
例えば、5月5日の端午の節句では菖蒲が、3月3日の上巳の節句(おひなまつり)では桃が使われます。
そして、7月7日の七夕の節句では、竹が重要な役割を果たします。
竹は中国から伝わったものであり、宮中行事として山や海の恵みを神に捧げるために竹を立て、五色の糸や布、提灯で飾りつけをします。
雅楽の演奏や和歌の詠み、そして裁縫や書道、芸事の上達を願う行事も行われます。こ
の行事は、江戸時代から庶民の間でも行われるようになりました。
竹を立てることは、神様や先祖様が地上に降りてくる目印となり、竹の中の空洞部分にその力が宿ると信じられています。
そのため、笹の葉は邪気を祓う神聖な葉とされています。
七夕飾りの短冊の書き方と作り方
七夕飾りの中でも短冊は重要な飾りの一つです。
短冊は細長い厚紙で、短歌や俳句を書くために使われるものです。しかし、七夕では折り紙を細長く切ったものが使われます。
七夕短冊の作り方
短冊の作り方は簡単です。
- 必要な材料を準備します。折り紙や色紙、または厚めの細長い紙を用意します。色紙の場合は、適当な幅に切り取ります。
- 紙を横に向け、上下に長くなるようにして配置します。
- 紙の右側から1cmほどの位置を下から切り込みます。この切り込みは、短冊を笹に付けるための留め具になります。
- 切り込んだ部分から上に向かって、縦に1cmほどの幅を残して切り離さずに切り進めます。これによって、短冊の形が作られます。
- 紙を裏返し、切り込みの部分を反対側に折り返します。これにより、短冊の形が固定されます。
- 短冊の先端部分を上に持ち上げ、笹に留める部分とします。笹の枝に差し込んで固定しましょう。
短冊の表面に、願い事や思いを書きます。思い浮かぶ言葉やメッセージ、願いを自由に書いてみましょう。
七夕短冊の書き方
準備をする
書くための短冊として、折り紙や色紙、または厚めの細長い紙を用意します。また、書くための筆記用具(ペンやマーカー)も用意します。
短冊の準備
短冊を手に取り、書きやすい位置を確認します。短冊の上部や真ん中、あるいは自分が好みの位置に願い事やメッセージを書くスペースを設けましょう。
願い事やメッセージの決定
自分の心の中で、七夕に込めたい願い事や思いを考えます。例えば、夢や目標の達成、家族や友人への感謝、幸せや平和を願うなど、自由に選びましょう。
書く
選んだスペースに、願い事やメッセージを書きます。字の大きさやスタイルは自由です。思いのままに文字を書き込んでください。
文字がうまく書けなくても心配ありません。大切なのは、自分の思いを短冊に込めることです。
見直し
書いた後は、書いた文字を確認しましょう。自分の意図した通りに書けているか、読みやすいかなどをチェックします。必要なら修正を行いましょう。
昔ながらの短冊に願い事を書く方法はこちらにまとめていますので良ければ読んでみてください。

このようにして、自分の思いや願いを短冊に書き込むことができます。
七夕の短冊は、自分自身や大切な人への願い事や感謝の気持ちを表現する素敵な手段です。
思いを込めて短冊に書き込んで、七夕の飾り付けを楽しんでみてください。
七夕と言えば織姫と彦星のお話ですが、七夕ストーリーを簡単にこちらにまとめていますので是非読んで見てください。



まとめ
七夕の飾り付けは、豊かな意味と願いを込めたアイテムで、夏の風物詩として楽しまれています。
紙衣や巾着、投網、吹き流し、折り鶴など、様々な種類の飾りがあり、それぞれに独自の象徴があります。
また、ひし形つなぎの意味、輪つなぎ、スイカやナスなど季節のものを飾る意味を紹介しました。
七夕には短冊も七夕の欠かせない要素となっています。
七夕の短冊には自分の願いや思いを書き込み、こよりに飾りつけることで、織姫と彦星に届けるとされています。
また、笹に縁起の良い飾りを施すことで、幸せや繁栄を願う風習もあります。
七夕の祭りを楽しみながら、思い出深い願い事や願望を込めた飾り付けを作りましょう。
家族や友人と共に、夏の夜空に願いを込めて短冊を飾り、心豊かなひと時を過ごしましょう。七夕の祝いを通じて、願いが叶うことを願っています。



コメント