
正月飾りは「いつ飾る?」「いつまで飾る?」と迷う方がとても多いです。
鏡餅・しめ飾り・松飾りは、基本的に【12月28日までに飾り、1月7日または15日まで】が目安とされています。
この記事では、正月飾りの種類ごとに、飾る時期・片付ける時期を分かりやすくまとめました。
正月飾りはいつから飾る?基本の考え方と目安時期
正月飾りの時期まとめ【保存版】
- 飾る時期:12月28日まで(遅くても30日まで)
- 外す時期:松の内まで(関東:1月7日/関西:1月15日)
- 鏡餅:鏡開きの日(一般的に1月11日)
正月飾りをいつから飾るか、飾る時期・片付ける時期は年神様をお迎えするための準備として大切なポイントです。
基本的には「正月準備が整ってから、無理のないタイミングで飾る」ことが考え方の軸になります。
一般的には、12月28日が縁起の良い日として広く知られています。
これは「末広がり」である八が付く日で、正月飾りを始める目安として選ばれることが多いためです。
- 12月13日(事始め):正月準備を始める日
- 12月28日:縁起が良く、最も一般的な開始日
- 12月30日:やむを得ない場合の目安
一方で、12月29日や12月31日は「一夜飾り」とされ、できれば避けたほうがよいとされています。
ここでは「いつから飾るか」の目安だけを押さえておき、しめ飾りやしめ縄の意味、飾る場所や正しい飾り方については、次の章で詳しく解説します。
しめ飾り・しめ縄はいつまで置く?「松の内」と片付け時期の目安

しめ飾りやしめ縄の飾る時期・片付ける時期は、「松の内」まで飾るのが一般的とされています。
松の内の期間は地域によって異なり、目安は以下の通りです。
- 関東地方:1月7日まで
- 関西地方:1月15日まで
松の内が終わったら、年神様をお送りする意味を込めて、
感謝の気持ちで外しましょう。
なぜ「松の内」まで飾るの?
しめ飾りやしめ縄は、年神様を迎えるための目印として飾られます。
飾りに使われている白い紙(紙垂)や水引にも、
それぞれ由来や意味があり、
単なる装飾ではなく「神聖な飾り」としての役割があります。
しめ縄・しめ飾りの意味や種類、白い紙の正体、
正しい飾り方や場所については、
正月飾りのしめ縄の意味と種類!しめ飾りの白い紙は?飾る場所と飾り方
で詳しく解説しています。
しめ飾りはどこに飾る?玄関飾りの意味と飾り方
しめ飾りはどこに飾る?
しめ飾りは、年神様をお迎えするために家の出入り口や神聖と考えられる場所に飾ります。
特に玄関は、年神様が家に入ってくる場所とされ、正月飾りの中でも最も重要な場所です。
しめ飾りは「いつまで飾るか」だけでなく、どこに・どのように飾るかも大切なポイントです。
特に玄関は、年神様をお迎えする最も重要な場所とされます。
玄関飾りの意味と飾り方
玄関に飾る正月飾りには、しめ飾り・しめ縄・門松などさまざまな種類があり、それぞれに縁起物や水引の意味が込められています。
また、玄関ドアに飾る場合は、左右どちらに付けるのが良いのか、マンションやアパートではどうするのかなど、迷いやすいポイントも多いですよね。
玄関飾りとしてのしめ縄の向き・裏白の正しい付け方を分かりやすく解説している記事があります。
玄関飾りに使われる縁起物の名前や意味、
玄関ドアへの正しい飾り方、
玄関に飾る正月飾りの種類や名前、
おしゃれに飾るコツ、ドアに取り付ける際の注意点については、
正月飾りに玄関を飾る縁起物の名前は?おしゃれなしめ飾りをドアに飾る方法
で詳しく解説しています。
鏡餅はいつから・いつまで飾る? – 鏡開きとの関係
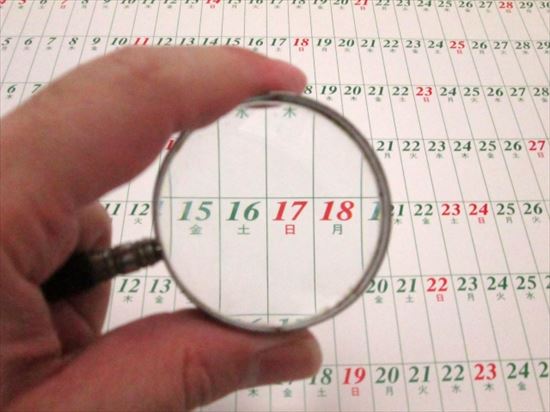
鏡餅は、年神様へのお供え物として特に重要な正月飾りです。
鏡餅の飾り方・置き場所・三方の意味
鏡餅は、飾る時期・片付ける時期だけでなく、
飾り方や置く場所、三方の使い方にも意味があります。
神棚や床の間が基本とされますが、現代の住宅事情に合わせた飾り方も増えています。
鏡餅を置く場所(玄関・神棚・床の間の正しい置き場所)や、
台座(三方・敷紙)の正しい向き、飾る意味については、
お正月の鏡餅の飾り方と飾る意味や置く場所!三方の置き方も紹介します
で詳しく解説しています。
飾る期間はしめ飾りとほぼ同じですが、片付けるタイミングは「鏡開き」に合わせます。
鏡餅はいつ下げる?鏡開きの意味と日付
鏡餅は、松の内が明けたあとに
「鏡開き」という行事で下げて食べるのが習わしです。
鏡開きの日は地域によって異なり、割り方や食べ方にも由来があります。
鏡開きの日にちや、
なぜ包丁を使わず手で割るのか、
「おすわり」と呼ばれる由来などについては、
正月の鏡餅の鏡開きはいつ?作法と「おすわり」と呼ばれる由来
で詳しく解説しています。
一般的には、1月11日に鏡開きを行い、この日に鏡餅を下げます。
地域によっては1月15日や20日に行う場合もあるため、地元の風習に合わせると良いでしょう。
まゆ玉・餅花など地域ごとの正月飾り
しめ飾りや鏡餅以外にも、
地域によっては「まゆ玉」や「餅花(もちばな)」と呼ばれる
正月飾りを飾る風習があります。
まゆ玉や餅花などは、豊作や家内安全を願って飾られる縁起物です。
これらも年神様を迎えるための正月飾りで、
飾る時期や意味は地域性が強く、
「小正月に飾るのか」「いつ片づけるのか」で迷いやすい飾りでもあります。
まゆ玉・餅花の意味や由来、
いつからいつまで飾るのかについては、
お正月飾りのまゆ玉や餅花の意味と作り方!いつからいつまで飾る?
で詳しく紹介しています。
正月飾りの処分方法と片づけ– どんど焼き or 自宅処分
正月飾りは、役目を終えた後も丁寧に扱うことが大切です。
多くの地域では、小正月に行われる「どんど焼き(左義長)」でお焚き上げをします。
神社や地域行事で回収してもらえる場合は、そちらを利用すると安心です。
どんど焼き・左義長で処分する場合
しめ飾りやしめ縄、門松、鏡餅などの正月飾りは、
地域で行われる「どんど焼き(左義長)」に持って行くのが最も一般的な方法です。
神社や地域行事として行われることが多く、
年神様をお見送りする意味も込められています。
自宅で処分する場合の注意点
近くでどんど焼きが行われていない場合は、自宅で処分しても問題ありません。
その際は、感謝の気持ちを込めて白い紙や半紙に包み、塩で清めてから可燃ごみとして処分するのが一般的です。
特別な塩や作法が必要なわけではありません。
地域の分別ルールがある場合は、それに従いましょう。
正月飾りを正しく整えて新年を迎えよう
正月飾りは、年神様をお迎えし、新しい一年の無病息災や家内安全を願うための大切な風習です。
- 飾る時期を守ること
- 外すタイミングを意識すること
- 感謝を込めて処分すること
この3点を押さえておけば、難しく考える必要はありません。
しめ飾りや鏡餅、門松などを正しい時期に整えることで、
年神様を気持ちよくお迎えし、新しい年を清々しく始めることができます。
地域によって風習や時期に違いがある場合もあるため、
ご家庭や土地の習わしに合わせて、無理のない形で取り入れてくださいね。
正月飾りの意味を知り、丁寧に準備と片づけを行うことで、
新年の始まりがより穏やかで心地よいものになります。
正月飾りの種類ごとの意味や飾り方については、本文中の関連記事も参考にしながら、ご家庭に合った形で取り入れてみてください。



コメント